エレクスはクライアントにとって意味があり効果につながるテストを設計・実行します。ミッションである「品質を追求し、つくりこむ。手戻りのない設計・開発の実現へ」を叶えるべくエレクスのテストにおいて考えていることをお伝えします。
01
テストにおける問題の本質
よく直面する問題と原因について、今一度本質を捉える
▽
02
Wモデル
上流の設計工程から参画する「Wモデル」という考え方
▽
03
上流工程からの参画
上流工程からの技術者参画でプロジェクトを成功に導く
▽
テストにおける問題の本質
よく直面する問題
機能や要件の優先順位がわからない
機能どうしのつながりがわからない
業務の流れがわからない
設計書がないか、あっても役に立たない
どんな仕様になっているかわからない
どんな結果が出れば正しいのかわからない
誰に聞いたらいいかわからない
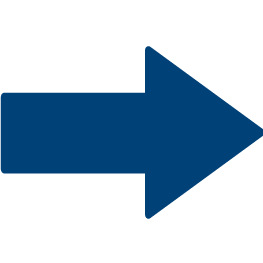
その原因
そもそも開発目的がはっきりしていない
業務分析を十分に行っていない
業務の流れがわからない
上流工程でドキュメントを残していない
要件定義を行った担当者がいなくなった
客先の担当者も代わってしまった
業務の流れがわからない
上記によく直面する問題と、その原因を記載しました。問題の本質を今一度考えてみたいと思います。テストにおける問題の本質は「テストのことは実装が終わってから考えればいいや」と思っていることです。 決まってその頃にはいろいろ大事なことが忘却の彼方に追いやられているのです。このことは、ある意味で「V字モデルの宿命」であるといえます。
上流の設計工程から参画する
「Wモデル」という考え方
そこでエレクスではテスト工程が迫ってからテスト技術者を集めるのでなく、上流の設計工程から参画させることを提案しています。 後でテスト設計をしなくてもよいということにはなりませんが、ソフトウェアの設計と並行してテストのことを考えることで、 確認すべき項目・必要な観点は何か?どんな環境を準備すべきか?といった、要検討事項・課題・リスクが予見でき、後工程に連携できます。
また、上流工程からのテスト参入はコスト面にも大きな影響を与えます。上流工程から技術者が参画することにより初期コストは多少増加しますが、後工程でのコストが大幅に削減され、結果的にコストを抑えることに繋がります。
上流工程からのテスト技術者参画で
プロジェクトを成功に導く
上流工程の経緯を知っている人がいてくれるため、人手をかけて調べる必要がなくなり、テスト設計者を少なくできる
確認すべき項目・必要な観点は何か?どんな環境を準備すべきか?といった、要検討事項・課題・リスクが予見できる
設計段階からテスト技術者を参画させることにより、有効な設計レビューができるので「品質の作りこみ」が可能となる
設計の段階で品質が作りこまれるため、下流工程での修正コストが大幅に削減できる
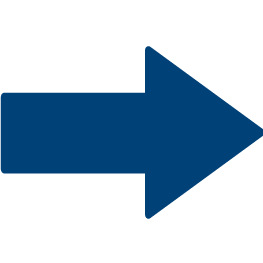
ミッション
MISSON
「品質を追求し、つくりこむ。
手戻りのない設計・開発」
の実現へ